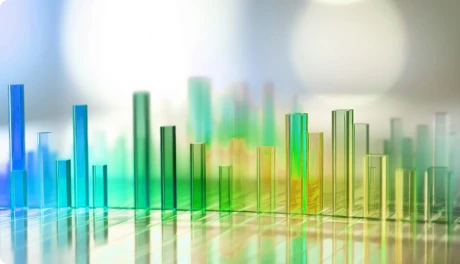サステナビリティ Sustainability
トップメッセージ
代表取締役 社長執行役員
西村 健からのメッセージ
マンダムグループのサステナビリティ
社会環境課題の解決に向けてサステナビリティ経営を根幹に据え、ESGスローガンでもある”BE ANYTHING, BE EVERYTHING.”(意味:なりたい自分に、全部なろう。)のもと、人それぞれが持つ本来の「自分らしさ」の表現に挑戦し続けられる持続可能な豊かな社会の実現に向けたお役立ちの進化と企業価値の創造を目指していきます。
サステナビリティ方針・体制・目標